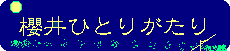眠れない墓
THE UNQUIET GRAVE
(三)
午後七時、街は週末のにぎわいに満ちていた。行き交う人々の間を縫って、男は小さな雑居ビルにたどり着いた。
エレベーターが停った。ドアが開き、目の前に黒地に白の素っ気ない看板が現れた。『jazz・spot ××××』と書いてあった。
扉を開けた。店内に客はいなかった。
「いいかい?」
「どうぞ。あれ、課長さんお一人ですか。めずらしいですね」
読みかけの新聞をたたみ、店主が立ち上がった。
「うん、土曜の夜の街なんて久し振りだ。景気はどうだい」
「閉店までこの調子です。いまどきカラオケの無い店なんて、流行るはずないですよ。それにこの頃の若い人は、ひとりで飲み歩いたりしませんしね」
「でも、音楽好きは来るんだろう」
「それはそうですが、めっきり減りました。ジャズのCDも廉価版が出回ってますから、わざわざここで高い金払って聴く必要もないんでしょう。・・・・・・たしか課長さん、この前来たときのボトルありましたね」
「いや、あれは仲間で入れたから、今日はショットで飲む。水割りをいただこうか」
「相変わらずお堅いですね。」
店主はあきれたように言った。
「実は、マスターに訊きたいことがあってね。音楽の事だ」
「ええ、どうぞ。わたしで解るジャンルだったら」
「『眠れない墓』という歌なんだが、ジャズではないけどご存知かな」
「知ってますよ。イギリスの古いバラッドですね。うちにもレコードがあるはずです。フランキー・アームストロングのうたってるのが・・・・・・」
店主はレコード棚を探し始めた。
「古いって、どのくらい昔の歌だね」
「ううん、曲としての完成は、少なく見積もっても三四百年前でしょう。同じイギリスでも、地方によって少しずつ違うメロディや歌詞で伝わっているそうですよ。さいきんこの手の音楽が、若い人にも聴かれるようになったんです。特にブルガリアンボイスやケルトのような、ヨーロッパの片隅で歌われてきた伝統音楽が」
「妙なものだね。ラップだかなんだかで踊り狂ってる彼等が、いっぽうでは古い異国の歌に耳をかたむけるとは」
「まるで胎内に還ったような、やすらぎを得られるからでしょう。楽しそうにしててもみんな疲れてるんですよ。ああ、あった。聴きますか」
「お願いするよ。歌詞はついてるかな」
「ええ、ついてますよ。対訳もありますから、読んでみてください」
レコードをターンテーブルに乗せて針を落とすと、店主は歌詞カードを男に手渡した。しっとりとした女性のアカペラがスピーカーから流れた。メロディや言葉の響きに小さな違いはあるが、たしかに女のうたうあの歌だ。
「この歌でしょう。それにしても課長さん、よくこんな渋い歌を知ってましたね」
「この間、知人が聴かせてくれてね。気に入ったものだから。ありがとう、間違いないよ」
男は礼を言って、歌詞カードに視線を下ろした。
「きれいなメロディからは想像もつかない、悲劇的な詩でしょう。イギリスの古謡には、こんなふうに死者の恋をテーマにしたものが多いんです」
店主の説明を聞きながら歌詞を読む男の顔色が、見る見るうちに青ざめた。
――これが、あの女の身の上。・・・・なんということだ。わたしが抱いたのは・・・・。ふたたび襲いくるめまいを、彼は必死にはね退けた。――ここで倒れるわけにはいかない。妻を、あの女から護らねば。
「だいじょうぶですか。顔色がすぐれませんよ」
「最近、貧血気味でね。ちょくちょく、めまいがするんだ」
「それじゃ、お酒飲んだらいけませんよ。わたしは奥さんにうらまれたくない」
「少しじっとしていれば治る。なにもいただかずすまないが勘定を頼む。それとタクシーを」
「はい、承知しました」
店主はタクシーを呼んだあと、水割り一杯分の勘定書きをさし出した。
「大切な事を教えてもらったのに、これだけでは心苦しい。全部取っておいてくれ」
男は一万円札を渡そうとした。
「わたしも商売人の端くれです。余分なお代はいただけません。うんちくはわたしの趣味ですからね。そのかわり体調が戻ったら、部下の女の子たちを連れてきてくださいよ」
「じゃあ、お言葉に甘えて」
「くどいようですが、奥さんのため、身体だけはいたわってください」
「あら、お早いこと。たまにはわたしの言うことを聞いてくださるのね。晩御飯まだでしょ。いま用意しますね」
妻は上機嫌で男を迎えた。
「頼れるのは、お前しかいないんでね」
「よく言います。身体の弱った時だけ素直なんですから」
台所に向かう妻の背中に、男は無言で呼びかけた。
――わたしの考えがたしかなら、お前と一緒にいられる時間もあと僅かだろう。さみしいけれど、これも自業自得だ。だが、これだけは約束する。わたしは自分の命にかえてもおまえを護る。たとえいっときにせよ、おまえを裏切ったわたしの、せめてもの償いだ。
男の想いに同調しながら、時計の針は刻一刻と進んでいった。
* * *
妻はすでに、すうすうと寝息をたてていた。男は静かに北の窓を開いた。
満天の星が今にも降りそうな、よく晴れた夜空だった。
男は眠らずに女を待った。その目で彼女の正体を見定めるために。
午前零時、急に睡魔が襲った。
――彼女が現れる時はいつもこうだ。眠ってはいけない。
男は気力で瞼を開きつづけ、窓の外をたしかめた。昨夜、夢に視た青い炎が、草むらを舞いながらこちらに近付いてくる。
――やはり、そうだったのか。
ぼんやりとした頭で思った瞬間、男は肩を叩かれた。
いつのまにか女が隣に立っていた。初めて会った夜の微笑みは失せ、いまは深い憂いが彼女の表情に翳をおとしていた。
二人は無言のまま丘に出た。女が口火をきった。
「どうして昨夜は会ってくれなかったんですか。わたしは苦しくて、胸が張り裂けそうでした」
「どうして? それはこちらが言いたいよ。ジューン」
「なぜ、わたしの名前を・・・・・・」
女は、虚を突かれたように茫然とした。やはり、男の予感は当たっていた。
「思い出したんだ、美術館で覧た君の絵を。そして君を描いた画家の、数奇な生涯も知った。君はおそらくこの世の人ではあるまい。『眠れない墓』、あれは、死者が墓の中から、生きている恋人に呼びかける歌なんだね。君がうたうように、死者とキスした者は生きられないとしたら、わたしももう永くはないだろう。自分はそれでもいい、でも妻は違う。妻は何も知らないんだ。わたしを信じきっている。すべてを知る必要は無い、と君は言った。しかしあとに遺す彼女の無事を願うと、わたしは真実を求めずにはいられない。恨みはしない、だからすべてを話してくれないか。お願いだ、ジューン」
「そこまでわたしのことをお調べになったんですね。なんという非情な。知らなければ、二人はいつまでも幸せだったものを。・・・・・・こうなった以上しかたありません。すべてをお話ししましょう」
「わたしは、たしかに生きている者ではありません。かといって、すでに死んだ者とも言い切れません。なぜなら、死にたくても死ねないのです。
あの人は、モデルであるわたしを愛するようになりました。『結婚してほしい』と彼はいいました。でもわたしの彼に対する感情は、どうしても尊敬の域をでることができません。思い悩んだ末、こう決心しました――純粋な画家とモデルの関係を保つため、このさい言葉を濁さずに、はっきりお断りしよう。
わたしは知らなかったのです。芸術家とは自信のみによって生きる人種、その誇りを傷つけられた時、彼らは狂人同様の振舞いにおよぶことを。いきなりわたしの胸を、彼のナイフが刺し貫きました。それ自体あっという間のできごとで、心臓が鼓動を停めるまで痛みを感じる間もないほどでした。しかし本当の復讐は、そのあとに待っていたのです。
あの人は、わたしの魂が永遠にさまよう事を願い、わたしの血を混ぜた絵の具で最後の仕上げを行いました。それが『眠らぬジューン・あるいは永遠の回廊』、あなたの覧たあの絵です。そして柱の影でわたしを見つめるのがあの人。
「それからわたしは、ひとり永遠の回廊をさまよい続けました。長く、寂しい歳月でした。そんなわたしに、あなたがかけてくれた優しい言葉。うれしくて涙がとまらなかった。もう一度あなたに逢いたい、募る想いが奇跡を呼び、とうとうあの絵を抜け出して、あなたに抱かれることができた。はてしない悲しみの日々に、やっと希望の光がさし込んだのに、あなたの心はいま、ふたたび奥さんのもとに帰ろうというのですね。
どうか、そんな薄情なことはしないで。わたしを捨てないでいてください。奥さんは、あなたがいなくなれば自ら命を絶つこともできる。けれど死をも許されぬわたしは、どうすればよいのです。いつまでもあなたの思い出を抱え、一枚のカンバスに描かれた眠れぬ墓の中、嘆きつづけねばいけないのですか」
そう言って女は、潤んだ瞳で男の目を見つめた。
哀れみが、いとおしさが、彼の胸につのる。さっきまでの固い決意が溶けていく。
男は無言で女に背を向けると、もと来た路を戻りはじめた。――わたしは、わたしはジューンを見捨てる事はできない。許してくれ妻よ。ひとり遺る悲しみを与えるより、いっそおまえをこの手で。
男は妻の枕元に立った。安らかに眠っている。震える両手が彼女の首に伸びた。あたたかい寝息を手首に感じる。
「あなた、明日も会社休んだら」
男は、はっとして手を引っ込めた。妻は、何事も無かったかのように、また寝息をたてている。寝言だった。両の手のひらを、男は愕然として見つめた。
――わたしはどうしたんだ。この手で妻を殺そうだなんて。
後悔が津波のように彼を襲った。あらためて妻の寝顔を見つめる彼の脳裏に、今日までの二人の日々がよみがえる。
機動隊に囲まれた大学のキャンパス、びしょ濡れの身体を寄せ合った若い日。恥ずかしさをこらえ、腕組歩いたポプラ並木の路。
男の両親は、旧家の跡取り息子が貧しい片親の娘と結婚するのに大反対だった。それを強引に押しきって、男は彼女を妻に迎えた。
父母は妻を嫁と認めても、けっして娘とは認めなかった。「子供ができぬのは女のせいだ」あからさまな厭味に、妻は黙って耐えていた。
――そんな両親の病床を最期まで看取ったのは、他ならぬこの妻ではないか。ふたりの結婚から生じたあらゆる苦労を、妻はひとりで受け止めてきた。彼女は彼女なりに、いつかくる幸せを夢みて、時にはくじけそうな心を支えてきたに違いない。それなのに何の権利があって、わたしがその人生の幕を引こうというのだ。葬られるべきは妻でなく、その夢を裏切ったわたしと、ジューンを苦しめる永遠の呪縛ではないか。
男はだらりと両腕をおろし、こうべを垂れた。
北向きの窓の外、すでに仲秋の星座たちが輝いていた。
* * *
朝もやにモノクロームの遠景が霞む。
風景が暗闇から景色を取り戻す一瞬の狭間・・・・・・
男は妻の枕元に手紙を置いた。今までのジューンとのいきさつが書いてある。これから彼が何をするつもりか書いてある。最後はこう締めくくってあった。
『少しでも長くおまえといたいが、それは許されない。わたしは、いつまたジューンの魔力に負け、おまえに手をかけるや知れぬ人間だから。
たぶん、お金の心配はいらない。実家の家屋と敷地は弟の物だが、残る土地や山林は、わたしの持ち物だ。それらを処分すれば生活には困らないだろう。
どうか一人になっても、今以上に幸せになっておくれ。わたしはここで、さよならを言うよ。楽しい日々をありがとう』
妻を起こさぬよう、そっと扉を開けて男は家を出た。手には黒い鞄と、ウイスキーの空き瓶二本を持っていた。男は納屋に入っていった。数分後に出て来た時、彼は膨らんだ鞄のみを抱えていた。
男は車に乗り込んだ。エンジンをかけ、サイドブレーキを降ろす。車は静かに動きだした。ルームミラーの中、住み慣れた我が家が小さくなっていく。忘れかけていた熱いものが胸にこみあげた。
車は美術館の駐車場に着いた。開館まで二時間以上ある。男は腕時計のアラームをセットし、座席を倒した。
――少し休もう。
覚悟が固まっていたせいか、意外なほどすんなり眠りに落ちた。
四章へ
|